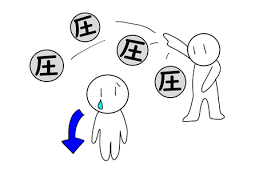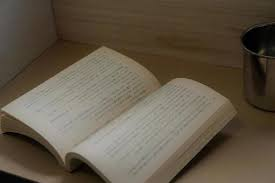高校に入って最初にぶつかる「新しい壁」、それが定期試験。
中学の定期テストとは色々と異なる点も多く、困惑してしまう方も多いのではないでしょうか?
そもそも一般受験の場合は受験本番に直接関係がなかったり、テスト期間がやたら長くてしんどかったり、問題が急に難しくなって点が取れなかったり…。
特に“自称進学校”と呼ばれるような学校では、定期試験の点数や順位がやたら重視されがちです。でも、そこでふと疑問が浮かびませんか?
そもそも、定期試験ってどこまで真剣に取り組むべきなの?
今回は、この「定期試験どうするか問題」について、少し掘り下げて考えてみます。
定期試験との付き合い方は工夫が必要

まず大前提として、定期試験をなめてかかると痛い目を見ます。
サボりすぎると赤点になって補習や追試、最悪の場合は留年のリスクも……。そこまで行かなくても、勉強習慣がなくなり、いい大学への合格が遠のくリスクは十分にあります。
とはいえ、真面目にやりすぎるのも危険。
毎回全教科を完璧に対策していると、それだけで平日も休日も潰れてしまい、肝心の「自分のための勉強」(=受験対策)が手につかなくなります。一人一人やるべき勉強って違いますし。
特に高3になると、やるべきことは格段に増えます。
それなのに、定期試験だけに時間を取られ続けるのは、正直かなりしんどい。
そんな状況で僕が辿り着いた結論は、教科ごとにメリハリをつけること。個人的には以下が最適解と踏んでおります。
・理科・社会・数学はしっかり対策する
・英語・国語はある程度、割り切る
ここからちょっと深堀りしていこうかと。
理科・社会・数学は実戦に直結する
まず理科や社会は、「覚えたことがそのまま得点に繋がる」典型的な教科です。
たとえば歴史で「鳴くよ(794年)ウグイス平安京」と覚えていれば、そのまま模試や入試本番で得点できます。

理科もここまでではないにしろ、知識で何とかなる部分は割とあります。まあ僕は思考力を問う問題が苦手だったので、理科はそこまででしたが…苦笑。
数学も、授業や定期試験で学んだ解法や公式が、模試や入試本番でもそのまま出てくることが多いです。積み上げ式の科目なので、定期試験の勉強=受験対策になりやすい。
ただし、注意点が1つ。
解法の“暗記”に偏りすぎると応用が効かないという落とし穴があります。
僕自身もそうだったんですが、「このパターンはこのやり方」だけで覚えてしまうと、ちょっと問題の角度が変わっただけで全然解けなくなる。
「なぜそうなるか?」の理解も一緒に深めておくことが、理数系では特に大事です。
英語・国語は暗記ゲー化しがち。割り切りも必要

一方で、英語と国語は定期試験との相性が微妙です。
特に“自称進学校”では、教科書本文の穴埋めや、文法問題、漢字テストが主で、「丸暗記しないと解けない」問題が多いんですよね。
たとえば英語の長文で、「エミリーは何歳ですか?」みたいな問題が出て、かつ文脈で答えが分からない場合、それはあくまでそのテストにしか通用しない代物。模試や入試にはまず活きません。
国語も同様に、「本文を完全に覚えてるかどうか」を問われる問題が多く、解釈力や論理力といった本質的な国語力とはかけ離れた試験になりがち。
僕も受験生のころ、英語や国語の定期試験対策をかなり真面目にやっていたんですが、今振り返ると「もう少し手を抜いてよかったな」と思います。
ただし例外もあります。
実力問題(長文読解や記述問題など)はちゃんとやるべきです。
こういった問題は確実に受験に直結するので、サボらず取り組みましょう。
定期試験を過度に冷笑するのも間違っている

ここまで読むと、「じゃあ定期試験ってやっぱ意味ない、当てにならないじゃん」と思うかもしれません。実際SNS上でもそういう考え方って少なからず見ますし。しかし、そういう極端な考えも危険です。
実際、定期試験の点数と模試の成績が完全に比例するわけではありません。
定期テストは微妙でも模試では全国上位、という人もいれば、その逆の人もいます。
だからといって、「定期試験なんて意味ない」「勉強する価値なし」と決めつけるのは、ただの言い訳になることもあります。
僕自身、成績が下がっていた時期はまさにこの思考でした。
「定期試験?あんなの暗記ゲーでしょ。受験には関係ないし、大事なのは模試だよ」って思ってました。しかし単なる言い訳だったんですよね。そもそも模試の成績も良くなかったですし。
定期試験に対して冷笑的になるのではなく、“受験とどう繋げていくか”という視点を持つことが大切だと、今振り返ってみて思います。
まとめ:定期試験は「使い方次第」で武器にもなる
定期試験にどう向き合うべきか?
その答えは、「目的と優先順位を明確にすること」に尽きます。
すべてを全力でやるのは不可能。教科ごとに強弱をつけよう
理科・社会・数学は受験対策と直結しやすいので、力を入れてOK
英語・国語は、暗記ゲー的な試験対策はほどほどに。実力問題に集中
「定期試験なんて意味ない」という言い訳には要注意
定期試験は避けて通れません。でも、やり方を間違えなければ、自分の学力アップにもちゃんと繋げられます。
「定期試験に追われる」から、「定期試験を使いこなす」へ。
この意識の違いが、受験勉強全体の質も変えてくれるはずです。